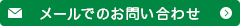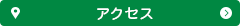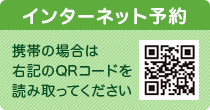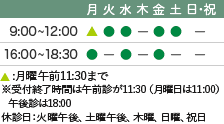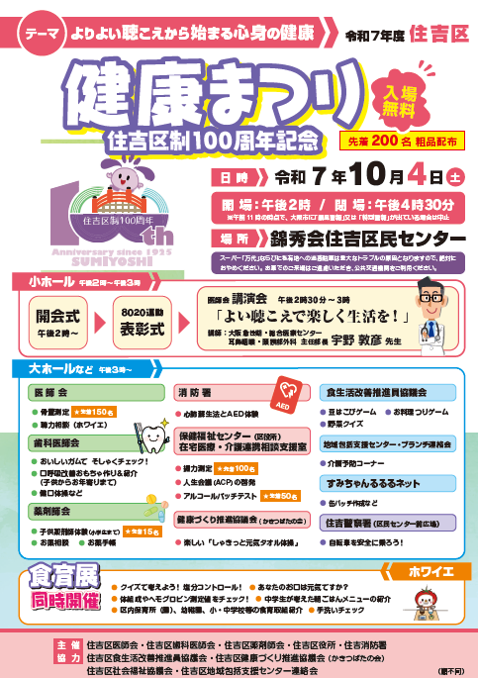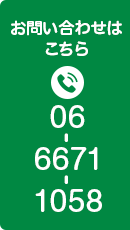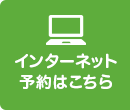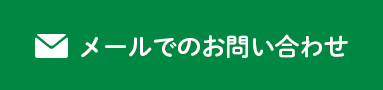1月13日(火)、14日(水)休診のお知らせ
都合により1月13日(火)、14日(水)を休診とさせていただきます。
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
評判の悪い補聴器について②
補聴器装用意欲の重要性とその背景
前回お伝えしたように、補聴器に慣れるまでには数週間から数ヶ月かかりますが、慣れれば日常会話が楽になり、生活の質が大きく向上します。しかし、医師や周囲の人間がいくら補聴器のメリットを説明しても、肝心のご本人がつける意欲を持たなければ、なかなか難しいのが現実です。
特に、高齢で一人暮らしの場合、話す相手がテレビくらいしかいないため、高額な補聴器は不要だと考える方が少なくありません。しかし、よく話を伺うと、以前は積極的に参加していた会合に、聞こえが悪くなったせいで会話ができなくなり、参加しなくなったというケースはよくあります。つまり、「聞こえない」→「会合に参加しなくなる」→「会話がなくなる」→「さらに聞こえが悪化する」という、難聴悪化のスパイラルに陥っているように思われます。
聴覚と社会生活、そして補聴器装用率の課題
聴覚は社会生活を営む上で非常に重要な機能です。聴覚が維持できないと社会から孤立し、その結果、運動機能や脳機能など、他の機能も低下し、最終的には寝たきりになってしまうといった寂しい晩年を過ごすことにも繋がりかねません。
このような状況を避けるためには、補聴器の装用が不可欠ですが、残念ながら日本の補聴器装用率は20〜30%と、欧米の70〜80%と比較して非常に低いのが現状です。これは大きな問題であり、欧米の手厚い補助金制度や、これまでの補聴器に対する悪いイメージも、装用を妨げる要因となっている可能性があります。
補聴器は高額な電化製品の一つで、耳かけ型で約10万円以上、耳あな型で約15万円以上が一般的です。しかし、補聴器の耐用年数は7〜8年とされており、片耳で10万〜15万円、両耳で20万〜30万円の出費を7〜8年に一度と考えると、果たして本当に高額なのでしょうか。
補聴器がもたらす多大なメリットと今後の展望
補聴器を装着して社会生活が維持されると、外出する機会が増え、歩行距離も伸びます。また、会話を通じて脳機能も維持されるため、認知症の予防にも繋がります。場合によっては、高血圧や認知症の薬など、大量の薬を服用している高齢者の場合、薬が不要になる可能性すらあります。
このように考えると、補聴器の普及は医療費削減にも繋がり、もう少し高齢者の補聴器に対する補助金が手厚くなれば、利用が進むことで、高齢者の聞こえが改善するだけでなく、社会生活の広がりや健康の維持、認知症の予防といった大きなメリットが生まれるでしょう。まさに、老後の幸せは補聴器が決め手になると言っても過言ではありません。
評判の悪い補聴器について
聴力の加齢性変化と補聴器の必要性
ご高齢になると、体のさまざまな機能が低下しますが、聞こえもその一つです。加齢による聴力の変化は、音を感知する内耳だけでなく、音を判断する脳の機能にも影響を及ぼします。聴力低下の程度には個人差が大きく、80代や90代でも若い頃と変わらない聴力の方もいれば、60代で補聴器が必要になる方もいます。
加齢性変化による聴力低下は、治療による改善が難しい場合が多く、聞き間違いが多い、テレビの音量を大きくしないと聞こえないなどの支障が出てきた場合には、補聴器の検討が必要になります。
補聴器に対する誤解と適応への道のり
一般的に、補聴器の評判はあまり良くないのが現状です。「高価な補聴器を買っても聞こえが良くならない」「うるさくてつけていられない」「自分の声が響く」といった不満から、結局使われずにしまい込まれてしまうケースも少なくありません。
これらの問題は単純ではありませんが、まず理解すべきは、高齢者が補聴器を使って音を聞くことは、若い頃の聞こえに戻るのではなく、「補聴器を介した新たな聴力を獲得する」ということだという点です。これは、義足をつけてもすぐに十分な歩行ができないように、補聴器も慣れるまでに根気強いリハビリが必要であることに似ています。
加齢とともに内耳の機能が低下し、脳に音の情報が伝わりにくくなると、脳は音に対して過敏になり、補聴器で大きな音を聞くと不快に感じることがあります。また、長年聴力が低下した状態が続くと、脳の言葉の判断能力も低下するため、補聴器で音を入れてもすぐに言葉の判別が改善するわけではありません。このため、初期には「音はうるさいのに言葉が分からない」と感じ、補聴器を外してしまうことがあります。
補聴器活用の成功と生活の質の向上
しかし、補聴器は継続して装用することで、徐々に音への慣れや言葉の判断能力が改善し、数週間から数ヶ月で効果を実感できるようになります。この期間、ご本人やご家族が毎日できるだけ長時間補聴器を使い続けるように励まし、サポートできるかどうかが、補聴器活用の成否を分けます。
補聴器がうまく活用できるようになると、会話がスムーズになり、ご本人だけでなく、ご家族や周囲の人々にとっても大きな喜びと満足が得られます。これは、コミュニケーションの大切さとその価値を再認識する機会にもなります。補聴器が適切に活用できるかどうかは、老後の生活の質に重大な影響を及ぼすのです。
当院では、無理なく補聴器に慣れていただけるよう、活用状況の把握や効果の確認を行い、きめ細やかな調整を重ねています。その結果、多くの患者様に満足のいく補聴器使用を実現しています。聞こえにくいことを年齢のせいだと諦めず、ぜひ当院にご相談ください。
8月5日(火)から8月15日(金)まで夏季休診とさせていただきます!
8月5日(火)から15日(金)まで夏季休診とさせていただきます。
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
人気ユーチューバーヒカキンさんと好酸球性副鼻腔炎
- 人気ユーチューバーヒカキンさんの手術動画
人気ユーチューバーのヒカキンさんが好酸球性副鼻腔炎になり手術を受け、その詳細を動画に公開したところ投稿後6日で855万回再生されています(【ご報告】指定難病になり入院して全身麻酔で手術することになりました)。
ヒカキンさんは子供のころからアレルギー性鼻炎で鼻が悪かったのですが去年から症状が悪化しついに手術となったようです。
- 好酸球性副鼻腔炎とは
好酸球性副鼻腔炎に関しては当院ホームページのコラム(隠れ好酸球性副鼻腔炎にご注意を | tada)でも取り上げております。以前はかなり希な病気とされておりましたがここ10年ぐらいで徐々に増加しここ数年当院で手術を受けられた方の約半数は好酸球性副鼻腔炎です。好酸球性副鼻腔炎は人の免疫機能が暴走した結果、好酸球がたくさん組織に出てくることにより炎症が起き副鼻腔という鼻の周りの空洞の粘膜が腫れたり粘っこい粘液が貯まり発症するのが原因です。
ヒカキンさんの場合粘膜の腫れにより目の上にある前頭洞という空洞の出口がふさがってしまい、飛行機に乗り、降下の際に空洞の内部で陰圧が形成されその結果激烈な頭痛がきたした為手術を決断されたようです。
- 好酸球性副鼻腔炎の症状と治療
ヒカキンさんのように激しい症状が出た場合は手術を含めた治療の必要性が理解されやすいですが、当院のコラムで紹介しているような粘っこい粘液がのどの奥に流れてくる後鼻漏や嗅覚障害や頭が重い感じなどの軽い症状が続いている方も多く、この病気を持っているにもかかわらずちゃんと治療を受けられていない方はかなり多いと思います。
特に診断面では見ただけでは専門の耳鼻咽喉科医でも正しく診断できないこともあり、CTスキャンなどによる画像診断が必要です。
またアレルギーの採血検査でもスギ、ヒノキやハウスダストなどのアレルギー物質に対する反応だけでなく白血球の中にどれぐらい好酸球が出ているかという検査も必要です。
アレルギー性鼻炎だろうと考えてアレルギーの薬や軽い抗生剤を服用しても良くならない場合やいったんよくなってもしばらくするとまた悪くなる場合は好酸球性副鼻腔炎の可能性を考えて検査をしっかり行いその検査結果に基づき治療を行うのが良いと思います。
好酸球性副鼻腔炎の治療で最も重要なのは手術治療でヒカキンさんも頑張って受けておられました。動画の中でもかなり手術や全身麻酔に関して不安を感じておられましたが、実際に手術となると大変不安を感じられると思います。その不安を解消するためにはできるだけ予想される事態やそれに対する対応を事前に詳細にご説明してご理解いただくことと、不測に事態が起きた場合に連絡できる体制を整えることだと思います。
ヒカキンさんは全身麻酔下に手術を受けられて手術前後に4日間入院しておりましたが、当院の手術は局所麻酔下、日帰りで行っておりますので特に患者さんご自身が術後の経過やそれに対する対応に関してご理解いただくことがかなり重要になってきます。
そのため当院では術後の経過を詳細に記載した文章をお渡しし、更に口頭でもご説明しご理解いただくよう努めております。その結果、患者さんからは大体術後の経過は説明通りでしたとおっしゃる方が多いですね。
またヒカキンさんは動画の中で「手術後に生きて帰ってくるぞ」などと、かなり重大なハードルを乗り越えるかのような発言をされておりましたが、不測の事態が起きる可能性は極めて低く、実際はあまり心配ないというのが実情です。
とはいうものの手術はやはり大変は大変で最終的には患者さんが納得して治療を選択しそれに沿って治療を行うべきで当院でも患者さんのご希望を最優先に治療を行っております。
いずれにせよ今回公開されたヒカキンさんの動画は大変良くできており、好酸球性副鼻腔炎が疑われる方や手術を検討している方、予定している方などには大変参考になると思います。
ラムゼイハント症候群とは?
- 葉加瀬太郎さんとラムゼイハント症候群
最近、バイオリニストの葉加瀬太郎さんがラムゼイハント症候群にかかられたことが話題になっておりました。
葉加瀬太郎さんは皆さんご存じの超有名なバイオリニストですが、実は私がトロンボーン奏者として参加している千里フィルハーモニア大阪と2度共演しておりまして、その際に直接お会いしたことがあります。本当に明るく気さくな方で日ごろはあまりなじまれていないクラッシック音楽も本当に楽しそうに生き生きと演奏されていました。
その葉加瀬さんが罹られたラムゼイハント症候群とはいったいどういった病気なのでしょうか?
- ラムゼイハント症候群の症状と原因
この病気は子供のころに罹って感染した水疱瘡のウイルスが体内に潜んでおり、体力の低下やお薬で免疫力が低下した際に暴れだして起こる病気です。
水疱瘡のウイルスは神経が大好きで感染すると神経を痛めつけてしまい、麻痺を引き起こします。
例えば顔面神経という神経に感染すると顔面神経麻痺がおこり顔の筋肉が動かなくなります。三叉神経という神経に感染すると顔面や耳の周囲の激しい痛みが起こります。
また、聞こえの神経や平衡機能の神経に感染すると難聴やめまいなどがおこります。加えて感染した部位の皮膚には水ぶくれや湿疹ができます。
- ラムゼイハント症候群の治療法と早期治療の重要性
治療はウイルスを撃退するお薬と神経の腫れや炎症を抑えるホルモン剤、神経の働きを改善するビタミン剤などを服用します。
なかなか改善しない場合や検査結果で神経の働きが強く障害されている場合は手術で顔面神経の周りの骨を削り圧迫を取り除く顔面神経減荷術という手術を行う場合もあります。治療が遅れると神経のやられた部位が広がり、改善に時間がかかったり麻痺が残ったりすることがあります。早期の治療が大切ということですね。
葉加瀬太郎さんは左の顔面神経がやられてしまったとのことですが、コンサートツアーも予定通り行われたとのことで、それほど重症でなければ改善する可能性が高いように思われます。しばらく時間はかかるかもしれませんがまたお元気な姿を拝見できればと思います。
暑い夏は耳鳴りや耳閉感、めまいなどの耳症状にご注意を!
毎日毎日暑い日が続いておりますが皆様、どのようにお過ごしでしょうか?
このように暑いとクーラーの効いた部屋にこもりがちになり体を動かす機会が減ると思います。
汗もかなり多くなり水分をとってもどうしても体の水分が減りがちになります。
また、気温が高いと血管が拡張しますので血圧が低くなります。そうなると血管の中の血液の量も減り、血液の性質もドロドロになり血の巡りが悪くなります。
そうなると全身の血の巡りが悪くなり体のあちこちに様々な症状がでますが、特に耳の奥にある内耳や耳管の周囲の血流が悪くなりますと内耳機能や耳管機能が低下し耳鳴り、めまい、耳閉感などの症状が出てきます。
実際当院の診察でも耳の症状を訴える患者さんが毎日毎日たくさん来院されています。そうならないためにはやはり暑い中でも体をより多く動かす必要がありますし、体を動かすとたくさん汗をかきますので十分な水分補給が必要となります。
また、体の疲れを十分とるためには睡眠を十分とる必要があります。
当院の近くにある若松神社でも夏越しの祈祷をされており、夏を無事に過ごせるようお祈りをしておりますが、やはりいにしえから夏をつつがなく乗り切るのに神様にお祈りをするほど大変なのだと思います。
やはり暑い夏をつつがなく過ごすためには神様にお祈りをしたうえで上記の対策を日常生活の中に取り入れていただくのが良いと思います。
アレルギー性鼻炎について
■データに基づくアレルギー性鼻炎の状況
アレルギー性鼻炎の代表格は、春先に皆さんが毎年苦しむスギ花粉症で、2019年のデータでは国民の約40%が病気を持っているといわれています。特に10代から50代の方に限ると約半数がスギ花粉症を発症しているといわれています。
さらにスギ以外の花粉症の方も25%に及び、スギ花粉症の方が多い10代から50代の方の約30%にスギ花粉以外の花粉症にり患しているといわれています。
しかもその割合は10年で大体10%増加してきておりますので2019年のデータから5年以上経ってさらに増加しているものと思われます。
■アレルギー性鼻炎の増加と対処法
春の花粉はマスコミでも大きく取り上げられることが多く注目されがちですが、スギ花粉以外の花粉症も増加してきています。
特に秋にはブタクサ、ヨモギ、カモガヤなどの花粉症に加えて温度変化によるダニ、ハウスダストによる通年性アレルギーの方も増えてきます。ですから、秋に急に鼻水が出てきて、鼻が詰まってきた場合、風邪ではなくアレルギー性鼻炎の可能性もあります。
風邪薬が効きにくい場合や風邪薬を中止するとすぐ症状が出てくる場合は、アレルギー性鼻炎の可能性が高く、適切な抗アレルギー剤の服用などの症状に応じた治療が必要となってきます。
最近は様々な抗アレルギー剤が市販されており薬局でも手軽に入手可能ですが、抗アレルギー剤は種類が多く、適切に選択しないと十分な効果が得られない場合もあり、なかなか症状が改善しない場合は、耳鼻咽喉科を受診した方が早く症状が楽になる場合も多いです。
■専門医の重要性と難治性副鼻腔炎の現状
さらに、最近では好酸球性副鼻腔炎というアレルギーが原因で発症する難治性の副鼻腔炎がかなり増えてきており、その場合はその病気の特別な治療が必要となる場合があり、耳鼻科での診断は大変重要になります。